フライフィッシングの道具の一つである「フライリール」について、個人的な思いを記しておきたい。
フライリールの記憶
まず、フライフィッシングにおいてフライリールの役割は、言うまでもなくフライラインを収納しておくためのものだ。そして時に、大物とのやり取りを助けてくれる──まるで相棒のような存在でもある。
私はフライフィッシングが大好きだが、今は少し距離を置いている。
しかし大人になった今、あの頃の情熱をもう一度手に取りたくなっている。
子供の頃、毎週末のように通っていた渓流。その記憶を胸に、今度は“精神哲学”のような感覚でこの釣りを嗜みたいと思っている。その想いが、今の私を静かにワクワクさせている。
そんなときに手に取った 『Fly Fisher Magazine EARLY AUTUMN 2025 No.317』。
ちょうどフライリール特集が組まれており、それが私にとってあまりにもタイムリーだった。
私の愛用するフライリールは、すでに存在しない釣具メーカー「コータック」の3/4番。
ドラッグ機能もないシンプルなモデルで、渓流や管理釣り場向けに作られたものだ。
このリールで「ヤマメ」「イワナ」「ニジマス」「オイカワ」「ウグイ」などを釣り上げた日々は、今でも懐かしく心に残っている。管理釣り場で40アップのニジマスを釣り上げたこともあったが、リールでやり取りすることはなかった・・・

フライリールには、驚くほど多彩な選択肢がある。
「ハーディー」「オービス」「セージ」──名門ブランドのリールはどれも魅力的で、所有するだけで満たされるだろう。
さらに「ティボー」「フィンノール」など、海を舞台にしたフライフィッシングのために設計されたリールもある(ここでは一旦割愛しよう)。
フライリールはシンプルな構造だからこそ、メンテナンスがしやすく、壊れにくい。
多少水に浸かっても、泥や砂を噛ませなければ、しっかり機能してくれる。
私のコータックのリールも、ほぼメンテナンスフリーで今でも機能する。
フライリールに何を求めるのか?
物質主義と資本主義が加速する現代において、
フライリールは単なる“巻き取り装置”以上の存在になっていると感じる。
制約のある手のひらサイズの丸いキャンバスに、
色・デザイン・質感・クリック音といった要素を詰め込み、
持つ者の所有欲をやさしく刺激してくる。
しかし、魚を釣るという一点だけを目的にするなら、
高級リールなど必要ないのかもしれない。
極論を言えば、「魚さえ釣れればいい」のだから。
だからこそ、私はこう問いたくなる。
フライフィッシングという行為は、いったい何なのか?
私はフライフィッシングが大好きだ。だが、それを特別扱いするつもりもない。
敷居を高くして閉鎖的な空気を作ってしまえば、
新しい世代を遠ざけてしまうだろう。
それはフライフィッシングの魅力を、自らの手で狭めることにもなる。
フライフィッシングというジャンルは、
フライフィッシャー一人ひとりのライフスタイルや哲学が色濃く反映される。
それは音楽で言うところのヒップホップに似ている。
ヒップホップが単なる音楽ジャンルではなく、
生き方そのものを示す言葉であるように、
フライフィッシングもまた「生き方の表現」なのだと思う。
そう考えると、シンプルな機構を持つフライリールという道具にこそ、
フライフィッシャー自身の哲学や価値観が宿るのかもしれない。
それは「長く使えるもの」を通して、自分の中に流れる時間と向き合う行為でもあるのだ。
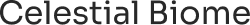



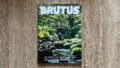
コメント